茅ヶ崎の税理士、吉井英人です。
業界に入る新入社員を見ていて、つくづくみなさん勉強家だな、と感じます。
「働きながら税理士を目指す」
なんとも良い響きです。
みなさん、熱い気持ちで勉強に取り組みますが、続けられる人はごくわずかです。
税理士を目指します!!と応募してくる方のうち、
全然勉強しない人→50%
勉強はじめるが短期でやめる人→30%
1年~2年頑張る人→10%
合格するまでやり切る人→10%
という感覚です。
働きながら税理士資格を取ることについて、なんとなく書いてみます。
働きながらの学習時間確保・スケジュール管理の工夫
- 税理士試験は科目合格制なので、1年に1~2科目ずつ着実に合格を狙います。この科目合格という言葉が税理士試験を取りやすく見せていますが、専門学校は短めに書いてますが、1科目のボリューム感は、1,000時間くらい。ボリュームの多い所得税法や法人税法は2,000時間くらいのボリューム感です。最初のうちは、簿記論と財務諸表論を1年目で取って、その後は税法を1年に1科目で4年間で合格します!!という人が多いですが、よく考えてください。9月~8月上旬まで実質11か月、1日3時間毎日勉強するんです。僕は勉強時間を残業時間のようにとらえて考えますが、毎日3時間の残業(勉強を)1年間休みなく続けてようやく1科目合格です。ボリュームの多い科目はこれを2年やってようやく合格です。
- スキマ時間や朝型勉強の人はなんとかこなしていって1科目~2科目取得する人もいますが、普通の人は途中であきらめます。ですが、5科目合格してはじめて税理士資格です。多くの人は10年間くらい時間を犠牲にして取得します。この持久力の高さが合格の秘訣になります。
モチベーションの維持・回復の方法(失敗やスランプからの復活)
- いろいろな方法があるかと思いますが、まず第一に絶対に合格するという強い決意を持ち続けることが1番です。途中で「取ってどうするの?」とか「税理士ってこれから不要になる職業じゃないの?」とか雑音が飛び交います。とにかく自分で決めたことだから絶対に最後までやり抜く意思を持つことが大事です。個人的には「余命宣告されてもこの資格は絶対取る。これに合格することが自分の人生の使命だ」くらいのマインドで勉強してました。
- 小さな目標設定と達成の繰り返しも重要です。勉強中は毎日の勉強時間を1分単位で記録していました。1日の目標は3時間と決めたら、必ず達成します。熱が出ても、家族旅行中でも、飲み会の翌日でも必ず達成してそれを記録していました。効率よりもとにかく実績を積み重ねました。やる気がでなければ、音楽を聴きながらでもお酒を飲みながらでも良いから必ず目標は死守しました。
- 税理士試験は大体どの科目も1回落ちました。そこから立て直すのは毎回なかなか大変でしたが、「不合格の次の年は合格の年」というキャッチフレーズで毎年立て直していました。毎年合格する人は本当に少数なので、不合格から立て直して合格できる精神力はとても大切な能力です。
学習法の選び方(通信講座・独学・スクール通学)
- 通信か通学かは正直どちらでもよいかと思いますが、税理士試験に関していえば独学はおすすめできません。試験の出題傾向や直前対策を専門学校が提供してくれるのに自分で試行錯誤しているのは時間の無駄遣いだと思います。やることは専門学校が用意してくれるので、それをスケジュール通りでこなしていくことが何より重要です。
資格取得が実務にもたらした効果・広がった業務領域
- 税理士事務所で仕事をしていれば、資格の有り無しにかかわらずお客様には信頼していただけると思いますが、「税理士の〇〇です」というだけで、信用力はだいぶ上がります。税理士にかかわらず「職業は〇〇です」と言える仕事に若いころ憧れましたが、今の若い人たちはどうなんだろう?
- 業務領域は、資格にこだわらなくても、拡げれば無限に広がります。でも多くの税理士は「税理士業」だけで手一杯なんだと思います。だから他士業の資格を取る人は少ない。仕事が請けきれないので、労務は社労士へ、補助金は中小企業診断士へ、と仕事を割り振る人がほとんど。だからこそ他士業の資格を取得して税務会計以外もやるのは確実に強みになります。
実際にあった苦労と乗り越えた工夫
- 働きながら勉強していて、一番大変だったのは気持ちの切り替えです。仕事で不安なことや、分からない事があった後に勉強をしようとしても気持ちが切り替わりません。工夫したのが、通学しているときに平日の夜2回(1コマ×2日)のコースではなく土曜の午前・午後で2コマこなすコースにしたことです。平日の仕事のことがいったんリセットされて土曜日にやることで気持ちがリセットできました。
- 家族を持ってからの勉強は、パートナーとなる人の協力が不可欠です。勉強時間の確保のために旅行に行くときも移動中の車や電車で少し勉強させてもらったりとか、キャンプ場で早起きしてランタンの灯りで外で勉強したこともあります。試験を受けられるのは家族の理解・協力があってのことだといつも意識していました。
- 社会人におすすめなのが、勉強も体力維持の運動もすべて仕事(タスク)ととらえることです。仕事をやらないという選択肢がないように、自分で決めた運動や勉強をやらないということはありえません。勉強も運動もすべてタスクと考えてこなしていきます。
とまあ、なんとなくまとめてみましたが、結局は精神論な気がします。
実際、根性あれば受かります。けっして頭の良さが必要なわけではありません。
やり続ける根性があればいつか必ず合格できます。受験生のみなさん、頑張ってください!!

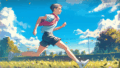

コメント